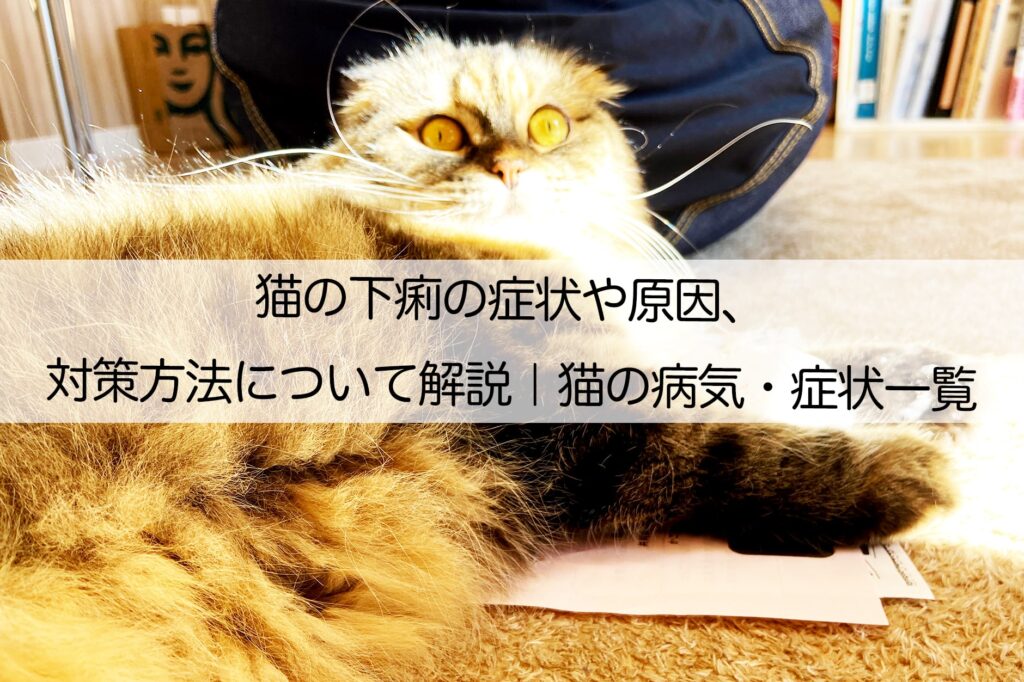「猫の様子がいつもと違う気がする。」

「猫が下痢になっているから心配だ。」
あなたは今、そうお考えではありませんか。
猫の様子がいつもと違って気になっている方や、猫の病気について知りたい方に向けての記事になります。

猫と暮らす上で知っておきたい猫の病気について、現役の猫の下僕が解説していくよ!!
今回は、猫の下痢の症状や原因、対策方法についてまとめました。
Table of Contents
猫の下痢の症状
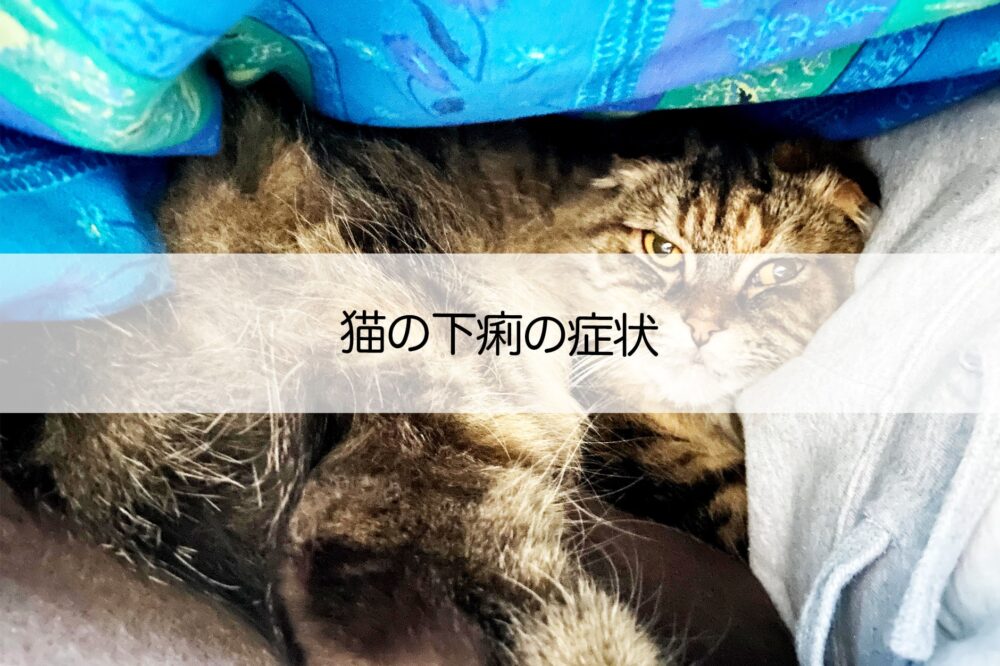
猫の下痢の時の症状一例
猫が急に下痢をした場合には心配になりますよね。
普段と違って柔らかい便や水便が出た場合、色がいつもと違ったり、血便が出た場合には注意が必要です。
上記の症状が見られる時に考えられる原因や対策を解説していきます。
その前に、まずは猫と暮らしている方には知っておいて欲しい健康な猫の便のチェックポイントについて一般論を解説します。
健康な猫の便のチェックポイント
猫の便が「いつもと違う!」と気づくためには、健康時の状態を知っておくことが重要です。
猫によって個体差もあるので、愛猫が健康なときの便の回数、色、量などを把握しておきましょう。
【回数】個体差あり
猫の個体差もあるので、なかなか回数の目安は示しにくいです。
私の愛猫はうんちの回数は1日1~2回が目安になっています。
その子の普段の回数と比べて多いか少ないかで判断すると良いでしょう。
早く気づければ早いほど、早期発見・治療が可能になりますので、少しでも気になることがあれば病院を受診することをお勧めします。
【色】基本的に同じ色
決まったフードだけを与えていれば、うんちの色は毎回同じ色のうんちになり便秘や血便の判断の目安になります。
赤ければ血便というのは誰でもわかりますが黒くても血便の場合があります。
胃からの出血ですとドス黒くコールタールのような軟便になります。
少しでも気になることがあれば病院を受診することをお勧めします。
おやつや人間のおかずを与えると毎日便の形や色は変化しますので見分けるのが困難となりますので、個人的には毎日同じフードを与えるのがおすすめです。
【量】個体差あり
健康時の1日の便量は、良質のフードは与えた量に比較して意外にうんちの量が少ないと言われています。
悪質なフードや肥満猫用のフードは与えた量に比較して、うんちの量が多いと言われています。
これは、満腹感を感じやすくするために、食物繊維を含むフードを食べると、うんちの量が多くなるからです。
【臭い】基本的に同じ臭い
決まったフードだけを与えていれば同じ臭いになるはずです。
異常な時の特徴的な臭いとしては「血液の臭い」や「硫黄の臭い」などがする場合には注意が必要です。
様々な症状がある
下痢
猫の下痢は、水分量によって形が変わります。
軟便の場合は、正常な便は比較的硬くコロコロしているのに、それより水分を多く含んだ柔らかい場合があります。
下痢の場合は、水分量が多めのほとんど形の無い水様の便になる場合があります。
血便
赤い血が混じっている場合は、肛門に近い大腸に何かしらの問題があると考えられます。
黒い血便は胃から小腸にかけての消化管のどこかに問題が発生し、出血後に血液が消化され黒い便になって出てきたものと考えられます。
また、ゼリー状の「粘液」が混じる「粘液便」は、主に大腸へのダメージがあるときによく見られます。
猫の下痢の原因

感染
ウイルス感染によって下痢が引き起こされる場合があります。
ウイルス性
代表的なウイルス性感染症は、パルボウイルスを原因とする「猫汎白血球減少症」や、コロナウイルスを原因とする「猫伝染性腹膜炎」などです。
前者は、3種混合ワクチンを接種することで、後者は完全室内飼育を心がけることで一定程度予防することができます。
ウイルス性感染症の場合は血清ウィルス検査などで検査をしてもらうのが良いでしょう。
細菌性
細菌を原因とする代表的な感染症は、カンピロバクター感染症が挙げられます。
カンピロバクター属菌がおなかの中にいても、多くの猫は症状を示しません。
ただ、免疫力の低い時期(子猫のときなど)や、体調が悪くなった時に、下痢や嘔吐を発症します。
寄生虫感染の有無を知りたい場合は便検査やPCR検査をしてもらうのが良いでしょう。
寄生虫性
コクシジウムや、線虫などといった寄生虫によっても下痢を起こします。
外で生活していた子猫などでは、感染していることも少なくありません。
症状がなくても、外で生活していた子を保護した場合には、一度は病院で調べてもらいましょう。
食事
食事によって下痢が引き起こされる場合があります。
消化吸収不良
消化吸収不良は、消化管の働きが悪い時に起こりやすく、主に食べ過ぎや、フードの種類が急に変わったりすることなどが原因で見られることが多いです。
食べ過ぎの防止には、ご飯を食べさせすぎないように計量して与えるのが良いでしょう。
また、フードを急に切り替えてしまうと、下痢をしたり嘔吐してしまうことがあるので、10日ほどかけて、毎日少しずつ切り替えていくとフードに猫の体が慣れてくれると思います。
食物アレルギー
様々な食物アレルギーが原因で発生する場合もあります。
原因となるアレルゲンを含まない食べ物を選ぶ必要があります。
もしも愛猫がアレルギーを持っていそうな症状があれば、アレルギー検査を病院で行うようにしましょう。
異物
異物によって下痢が引き起こされる場合があります。
薬物や中毒物質、異物を飲み込んでしまうことで下痢を引き起こしてしまうことがあります。
異物を飲み込ませないようにするには、床に危ないものを放置しないのが良いでしょう。
もしも異物を飲み込んでしまった場合には、かかりつけの獣医に相談しましょう。
病気
病気によって下痢が引き起こされる場合があります。
感染症など以外の病気で引き起こされる場合は、膵臓や肝臓、内分泌の病気や、消化器の病気などが考えられる場合があります。
ストレス
ストレスによって下痢が引き起こされる場合があります。
ペットホテルや病院で知らない環境にいたり、家に人がいない時や、引っ越しなどで環境が変わってしまうと、ストレスを感じて元気がなくなることがあります。
その場合は一過性なので、しばらくすると回復することが多いですが、そういった要因がないあるいは長く続く場合には、別病気の可能性がありますので、早めにかかりつけの獣医に相談しましょう。
猫の下痢の対策方法
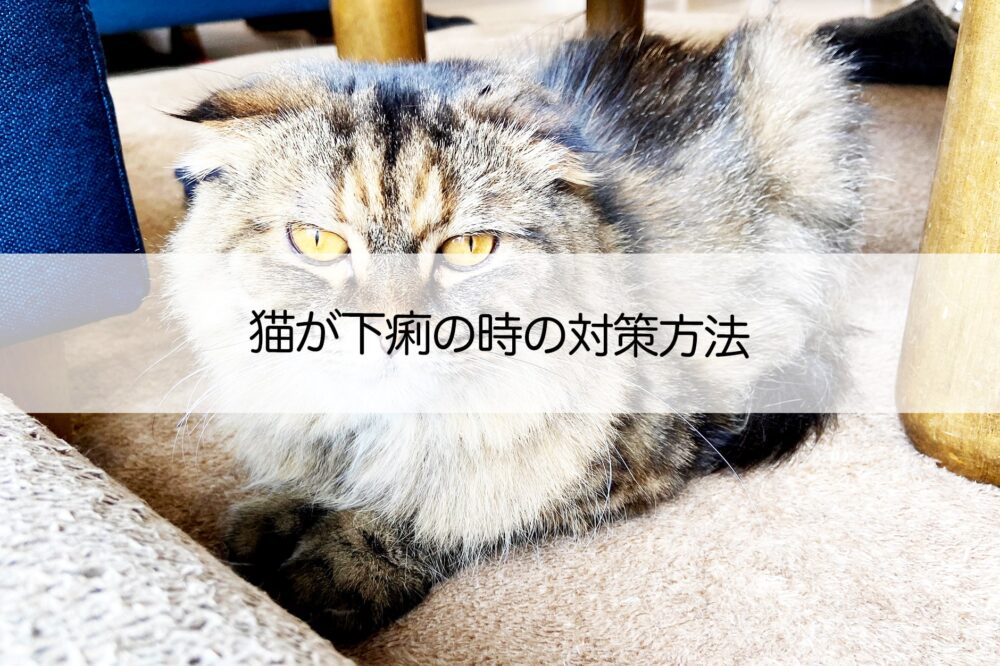
健康な猫の便のチェックポイントでお伝えしたように、猫の健康時の便の状態をしっかりと知っておくことが重要です。
健康時と違う様子が見られるようであれば、かかりつけの獣医に相談しましょう。
早く気づければ早いほど、早期発見・治療が可能になりますので、少しでも気になることがあれば病院を受診することをお勧めします。
【関連記事】愛猫家がおすすめする猫のペット保険人気8選【2021年最新版】
愛猫家がおすすめする猫のペット保険人気8選【2021年最新版】はこちらから↓

ペット保険の一括見積もりサイトはこちらから↓↓