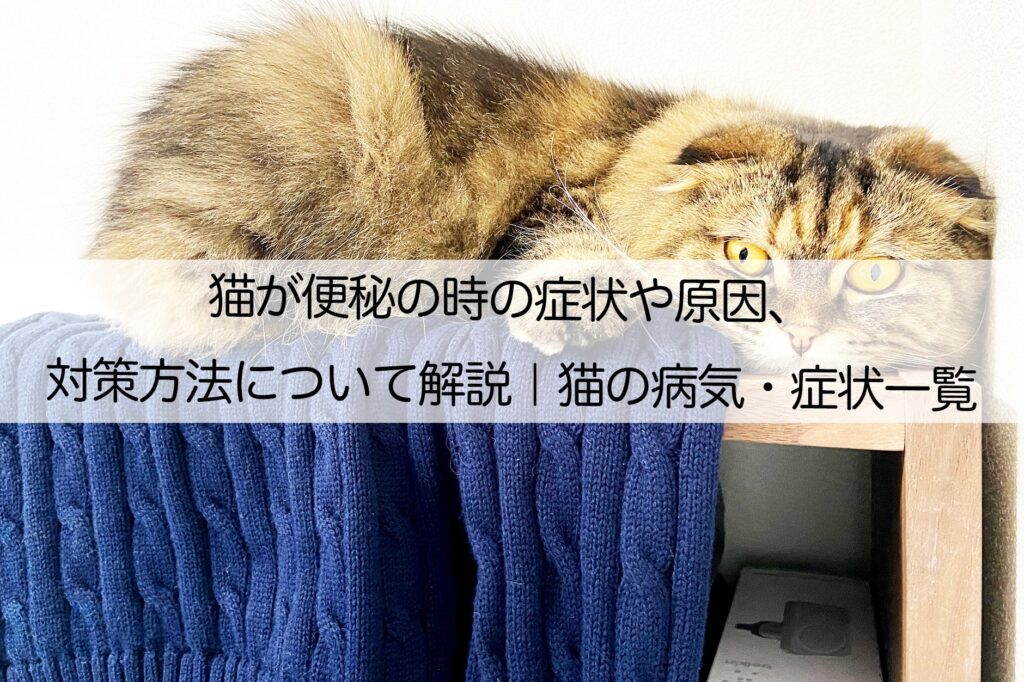「猫の様子がいつもと違う気がする。」

「猫の血尿が出たから心配だ。」
あなたは今、そうお考えではありませんか。
猫の様子がいつもと違って気になっている方や、猫の病気について知りたい方に向けての記事になります。

猫と暮らす上で知っておきたい猫の病気について、現役の猫の下僕が解説していくよ!!
今回は、猫が便秘の時の症状や原因、対策方法についてまとめました。
Table of Contents
猫が便秘の時の症状
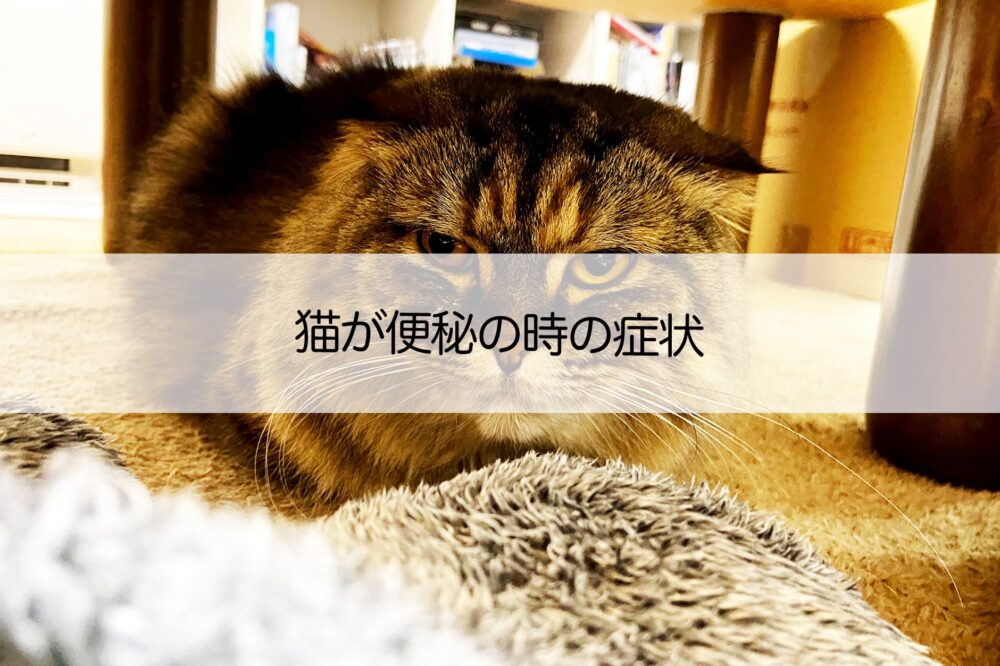
猫が便秘の時の症状一例
猫が便秘の場合には心配になりますよね。
普段と違って便が硬い場合や、排便時に時間がかかっている場合には注意が必要です。
また、出したいのに出なさそうな場合や、出たとしても少量しか出ない場合、何回もトイレに行こうとする行動にも注意しましょう。
上記の症状が見られる時に考えられる原因や対策を解説していきます。
その前に、まずは猫と暮らしている方には知っておいて欲しい健康な猫の尿のチェックポイントについて一般論を解説します。
健康な猫の便のチェックポイント
猫の便が「いつもと違う!」と気づくためには、健康時の状態を知っておくことが重要です。
猫によって個体差もあるので、愛猫が健康なときの便の回数、色、量などを把握しておきましょう。
【回数】個体差あり
猫の個体差もあるので、なかなか回数の目安は示しにくいです。
私の愛猫はうんちの回数は1日1~2回が目安になっています。
その子の普段の回数と比べて多いか少ないかで判断すると良いでしょう。
早く気づければ早いほど、早期発見・治療が可能になりますので、少しでも気になることがあれば病院を受診することをお勧めします。
【色】基本的に同じ色
決まったフードだけを与えていれば、うんちの色は毎回同じ色のうんちになり便秘や血便の判断の目安になります。
赤ければ血便というのは誰でもわかりますが黒くても血便の場合があります。
胃からの出血ですとドス黒くコールタールのような軟便になります。
少しでも気になることがあれば病院を受診することをお勧めします。
おやつや人間のおかずを与えると毎日便の形や色は変化しますので見分けるのが困難となりますので、個人的には毎日同じフードを与えるのがおすすめです。
【量】個体差あり
健康時の1日の便量は、良質のフードは与えた量に比較して意外にうんちの量が少ないと言われています。
悪質なフードや肥満猫用のフードは与えた量に比較して、うんちの量が多いと言われています。
これは、満腹感を感じやすくするために、食物繊維を含むフードを食べると、うんちの量が多くなるからです。
【臭い】基本的に同じ臭い
決まったフードだけを与えていれば同じ臭いになるはずです。
異常な時の特徴的な臭いとしては「血液の臭い」や「硫黄の臭い」などがする場合には注意が必要です。
猫が便秘の時の原因
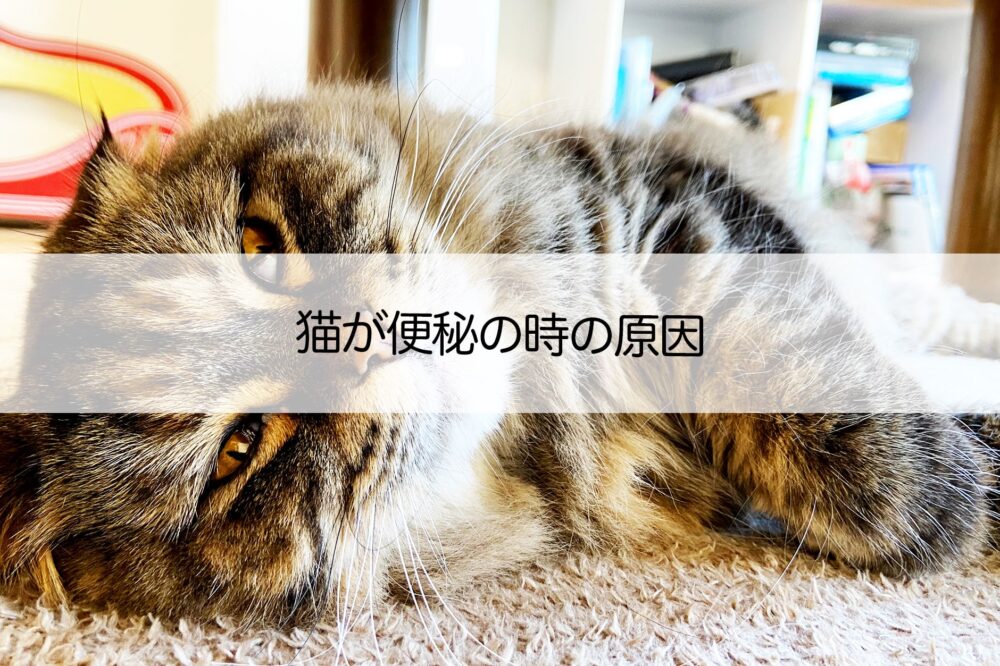
病気
慢性腎不全
慢性腎不全とは、様々な原因により腎臓の機能が時間をかけてゆっくりと低下していく病気です。
水をたくさん飲んでも多尿によって便の水分が減ってしまうので、便秘の原因にもなると言われています。
猫の場合、加齢に伴い腎機能が低下するケースが多く、特に7歳以上の猫によくみられる病気です。
腎臓には様々な機能がありますが、その中でも血液の中の老廃物をろ過し、尿をつくるという大切な役目を担っています。
腎臓病にかかると、腎臓の機能が低下していくため血液中の老廃物をろ過することができず、毒素が体の中に溜まって、様々な障害を引き起こします。
腎臓は一度悪くなると再生はできないため、腎臓病を早期発見し、いかに進行を遅らせて残りの機能を維持することが重要になります。
初期の段階では食事療法や新鮮な水分を取らせることも大切になってきますので、腎不全が疑われる場合には早めにかかりつけの獣医に相談しましょう。
腸閉塞による通過障害
腸閉塞による通過障害とは、腸内に異物や毛玉などが溜まって、腸の流れが滞ってしまう病気です。
特に長毛の猫は毛玉が溜まりやすいので注意が必要です。
腸の中のものが排出されにくくなるので、便秘の原因になります。
この病気かを見極めるためには特に、嘔吐が連続してあった場合には腸閉塞の疑いを持つと良いでしょう。
骨折
骨盤など下半身のどこかが骨折してしまっている場合、排便するためにうまく力を入れる事が出来ず、そのまま便秘になってしまう事があります。
また猫の骨盤を骨折した場合は骨折した骨に直腸が圧迫され便が出づらくなることもあります。
もしも骨折の可能性があるのであれば、早急に病院へ連れていきましょう。
生活習慣
日常生活の中には便秘になりやすい生活というのも存在します。
- 食事の量が少ない
- 好き嫌いが激しい
- 普段から水分を摂る量が少ない
- ドライフードをあまり使っていない
- 運動をあまりせず、寝てばかりいる
人間も同じですが、上記のような食生活だと便秘になりやすい傾向があります。
日頃から、猫の体調や習慣を観察して、便秘にならないようにしてあげることが重要です。
ストレスによる便秘
多頭飼いのストレスによる便秘が考えられます。
加齢に伴う便秘
10歳以上の高齢猫の場合、便秘は多くの飼い主が経験する悩みと言われています。
2〜3日程度の便秘であれば、様子を注意してみておけば命に関わることはありませんが、それ以上便秘が続く場合には、病院に連れていくようにしましょう。
高齢猫の場合、腸の運動が鈍ってきてしまい、うまく排便しきれず便秘になる場合があります。
また、何らかの理由で便秘が慢性化すると結腸内に便がたくさん溜まってしまう「巨大結腸症」になり、便秘が悪化する可能性があります。
巨大結腸症を発症するまでの状態になってしまうと、もはや自力での排便が困難な状態です。
人の手による摘便など、動物病院で治療が必要な状態となります。
猫は犬に比べ、もともと便秘になりやすい動物と言われています。
健康な猫の便のチェックポイントでお伝えしたように、猫の健康時の便の状態をしっかりと知っておくことが重要です。
日常的に便の固さ・量・回数を注意して観察しておきましょう。
猫が便秘の時の対策方法
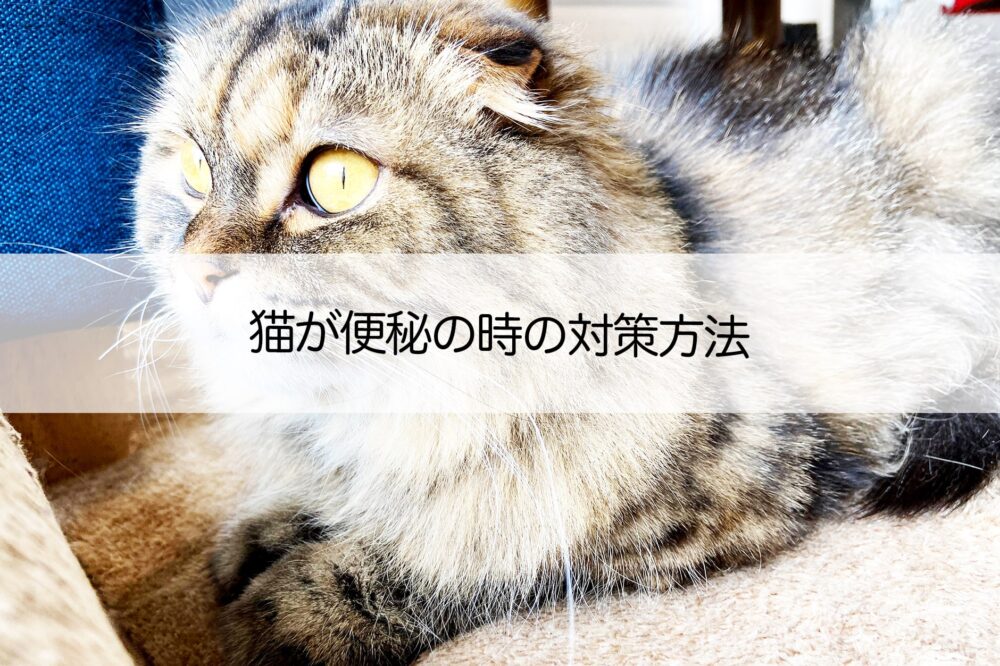
健康な猫の便のチェックポイントでお伝えしたように、猫の健康時の便の状態をしっかりと知っておくことが重要です。
健康時と違う様子が見られるようであれば、かかりつけの獣医に相談しましょう。
早く気づければ早いほど、早期発見・治療が可能になりますので、少しでも気になることがあれば病院を受診することをお勧めします。
【関連記事】愛猫家がおすすめする猫のペット保険人気8選【2021年最新版】
愛猫家がおすすめする猫のペット保険人気8選【2021年最新版】はこちらから↓

ペット保険の一括見積もりサイトはこちらから↓↓