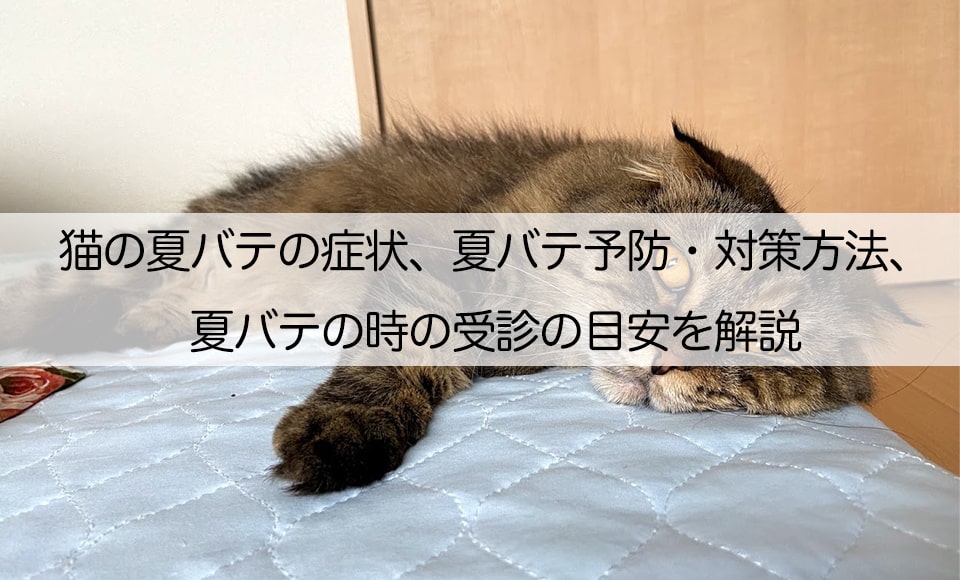毎日猛暑が続いていて、体調を崩したり、食欲がなかったりと夏バテになりがちですよね。
飼い猫も夏バテをしているのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、猫の夏バテの症状、夏バテ予防・対策方法、夏バテの時の受診の目安をまとめました。
Table of Contents
猫も夏バテする?
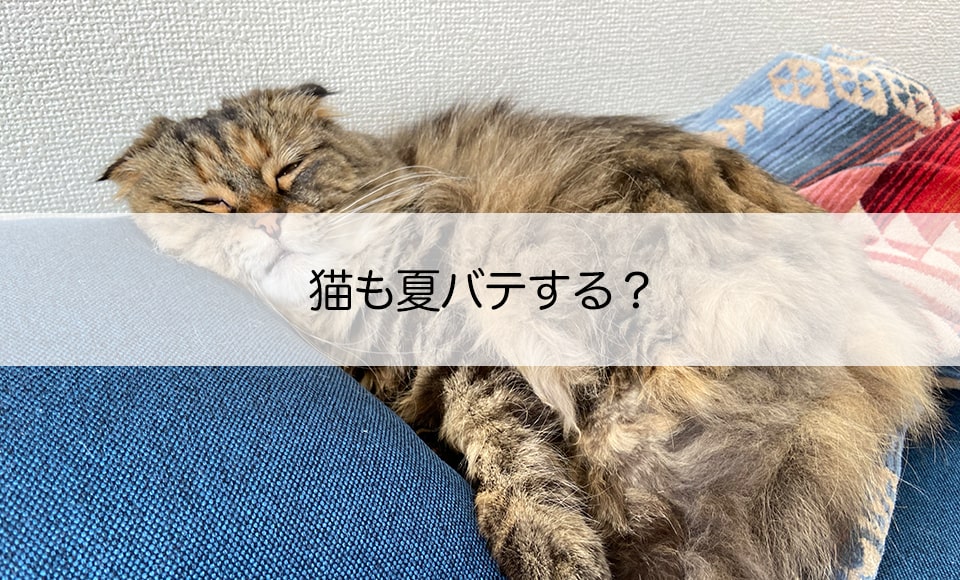
猫は、比較的夏バテにはなりにくい生き物とされています。
比較的暑さに強い理由として、猫のルーツが関係しています。
一般的に飼育されている「イエネコ」のルーツは、砂漠やジャングルに生息していたリビアヤマネコと言われています。
※普段家で飼っている猫や野良猫とされている猫は、学名ではイエネコと呼ばれる動物です。
リビアヤマネコは、暖かい場所を好むので、暑さにはある程度耐性があると言われています。
しかし、高温多湿な場所に長時間いると夏バテを起こす場合があります。
猫は汗腺が少なく、人間のように発汗作用による体温調節ができません。
そのため猫は、蒸し暑い日には涼しい日陰を見つけて寝転がったり、冷たい床や家具に体をくっつけて体温を下げたりします。
暑い日に密閉された部屋や車の中に放置しないようにしましょう。
特に窓を閉めた車の中では想像以上に急速に温度が上昇し、猫だけでなく人間も熱中症になってしまうことがあります。
猫の夏バテの症状

①普段よりご飯を食べない、ご飯を食べなくなった
普段食べているご飯を食べなくなってしまったり、極端にご飯を食べる量が減っている場合、夏バテによる食欲不振の可能性があります。
人間も暑い日には、食欲が減ったり、ご飯が食べられないことがありますが、猫にもそういった症状が出ます。
猫がご飯を食べてくれないからと言って、別のフードに急に切り替えてしまうと、下痢をしたり嘔吐してしまい内臓に負担をかけてしまいますのでやめましょう。
しかし、本当に全く食べない状態が36時間以上続く場合には、脂肪肝(肝リピドーシス)と呼ばれる別の病気の可能性もあるため、24時間様子を見て全くご飯を食べない場合は早めにかかりつけの獣医に相談しましょう。
②水を飲まない
猫は元々たくさん水を飲む生き物ではありません。
しかし、夏バテで食欲不振になると水も飲めなくなる猫もいます。
水分が足りなくなってしまうと夏バテから脱水症状を引き起こしてしまうこともありますので、トイレの回数をチェックしたり、水を飲んだか毎日確認してあげるようにしましょう。
③普段より元気がない、ぐったりしている
普段よりぐったりしていたり、だるそうにしているのも夏バテの症状です。
夏の暑い日も普段通り寝て過ごすことが多いのが猫ですが、ご飯の時間になっても起きてこない場合や、普段活動している時間にもかかわらず寝ていて声をかけても寄って来ない場合には注意が必要です。
おやつなどの猫の好物を与えても、興味を示さない場合、夏バテしている可能性が高いです。
なるべく涼しい部屋に移動させたり、ずっとぐったりしている場合には早めにかかりつけの獣医に相談しましょう。
④下痢や嘔吐を繰り返す
猫は元々嘔吐をしやすい生き物ですが、それは普段毛繕い(グルーミング)で溜まった毛玉を排出するために嘔吐します。
毛玉を排出する以外の嘔吐が頻繁にある場合は、胃腸が弱っている可能性が高いので早めにかかりつけの獣医に相談しましょう。
夏バテになりやすい猫種
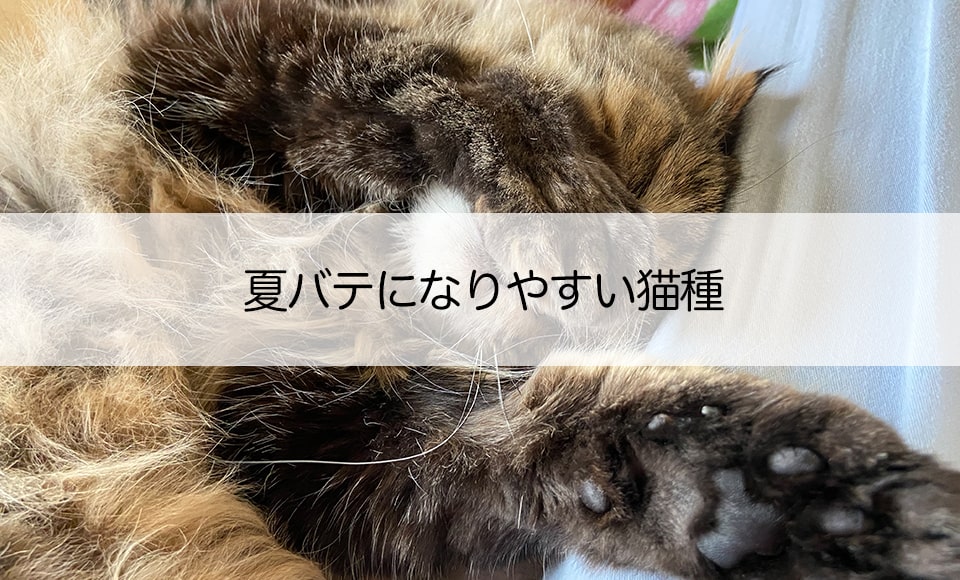
長毛種
長い毛をもつ猫のことを長毛種と言います。
長毛種の猫は、ルーツが寒い国であったりすることから、体温を外に逃す必要がなかったため、夏場に体温をコントロールすることが苦手です。
短頭種
短頭種(たんとうしゅ)とは、エキゾチックショートヘア、ペルシャ、チンチラのような、鼻がぺちゃんとしている猫の種類のことを言います。
先天的な特徴で、鼻の穴が小さく、気管も細いため、「短頭種気道症候群」になりやすい品種と言われています。
鼻の穴が小さく、気管も細いことが原因で、唾液を気化させ熱を逃して体温をコントロールするのが苦手です。
肥満気味の猫
肥満気味の猫も夏バテしやすいです。
肥満体型だと、脂肪によって体内に熱がこもりやすくなってしまいます。
重度の肥満だと首回りにも脂肪がついてしまい、呼吸もしにくくなってしまいます。
もしも、猫にダイエットさせるのであれば夏場のダイエットは、猫の体に負担をかけるのでお勧めできません。
ダイエットをさせるのであれば、夏が来る前もしくは夏が過ぎた後にダイエットさせるのが良いでしょう。
高齢の猫
人間もそうですが、高齢になると体の機能が衰えてくるので、夏バテしやすくなります。
体温調節機能が衰えてきますので、冷やし過ぎず、暑過ぎず快適な気温を保ってあげることで夏バテを予防できます。
夏バテ予防・対策4つの方法
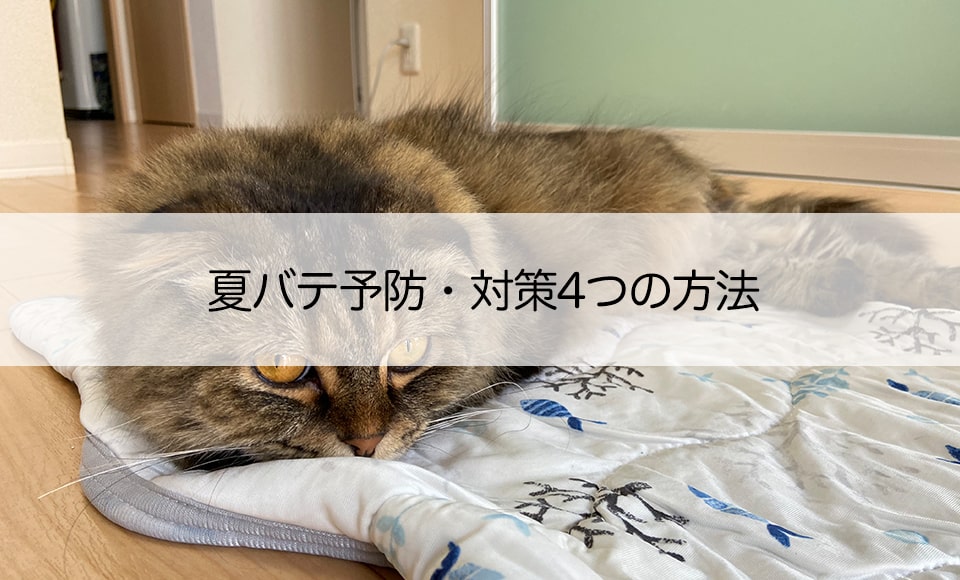
①水を多く飲ませる
水分不足は夏バテの原因です。
新鮮な水を部屋の複数箇所に設置したり、水が循環する給水器を導入すると、猫は喜んで水を飲んでくれやすいです。
水分を摂るのが苦手な猫ちゃんには、ドライフードを少し水でふやかしてあげたり、ウェットフードは水分量が高いものが多いので、ウェットフードをトッピングしたりすると水分を摂取しやすいです。
②食欲を湧かせる
夏バテしてフードを食べる量が減ると、体力も落ちてしまいます。
いつもあげているフードの食いつきが悪い場合には、いつものキャットフードにトッピングをすることで食いつきが上がることがあります。
トッピングには、猫用の鰹節やふりかけ、ウェットフードをいつものフードの上からかけてあげましょう。
ドライフードに不足しがちな水分を補うためにウェットフードをトッピングしてあげたり、猫ちゃんが好きな食材をトッピングしてあげると喜んで食いつく可能性が高くなります。
③快適な気温・環境
猫が快適と感じる気温は22〜28℃と言われています。
猫は暑いのも苦手ですが、何より苦手なのはジメジメとした湿度の高い場所です。
気温が高い日だけでなく、湿度が高い日はエアコンのドライ運転を使って快適な環境を整えてあげることで、夏バテ予防になります。
④ひんやりグッズを使う
ジェルマットやアルミマット、大理石のマットなどを利用することで、猫の体がひんやりと快適にすることができます。
いろいろなタイプのグッズがありますので、猫ちゃんの好みやおうちのインテリアに合わせて選ぶと良いでしょう。
夏バテの時の受診の目安は?
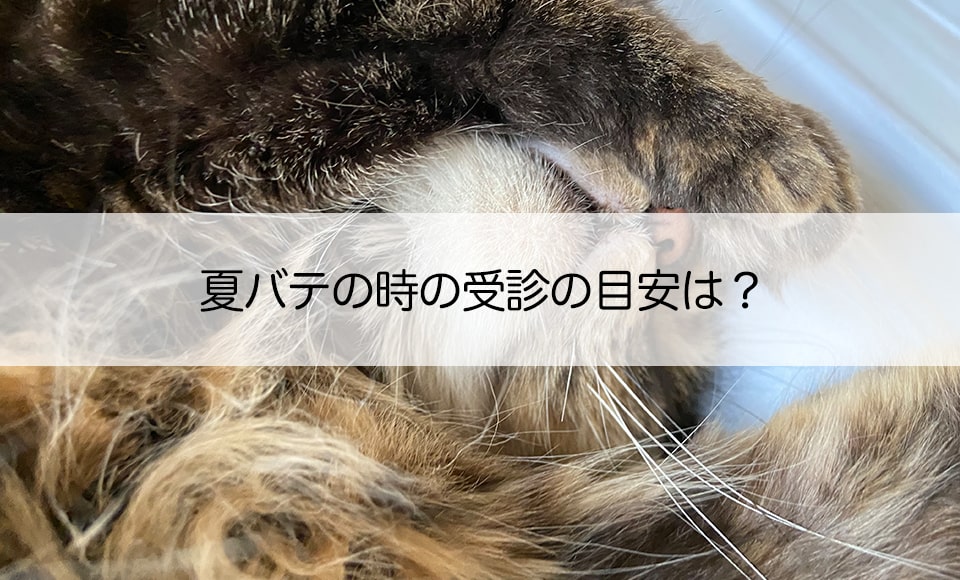
食欲の低下や、食事を摂らなくなってしまった時、あるいは下痢や嘔吐などの消化器系の症状が出た場合にはなるべく早く受診しましょう。
猫は痛みに強い生き物と言われていて、不調を表に出さない子が多いので、普段と様子が違う場合にはかかりつけの獣医に相談しましょう。
ただし、換毛期である5〜6月には毛繕い(グルーミング)で溜まった毛玉を排出するために嘔吐しやすい時期になります。
こまめにブラッシングしたり、毛玉を体外に排出しやすいフードを与えるなど工夫してみるのも良いでしょう。
猫の夏バテの症状、夏バテ予防・対策方法、夏バテに効くフードのまとめ
猫の夏バテの症状、夏バテ予防・対策方法、夏バテに効くフードについては以下のまとめを参考にしてください。
- 猫の夏バテの症状として、①普段よりご飯を食べない・ご飯を食べなくなった、②水を飲まない、③普段より元気がない・ぐったりしている、④下痢や嘔吐を繰り返すなどがあげられる。
- 夏バテになりやすい猫種として、長毛種、短頭種、肥満気味の猫、高齢の猫がなりやすい。
- 夏バテ予防・対策方法として、①水を多く飲ませる、②食欲を湧かせる③、快適な気温・環境、④ひんやりグッズを使うなどがある。