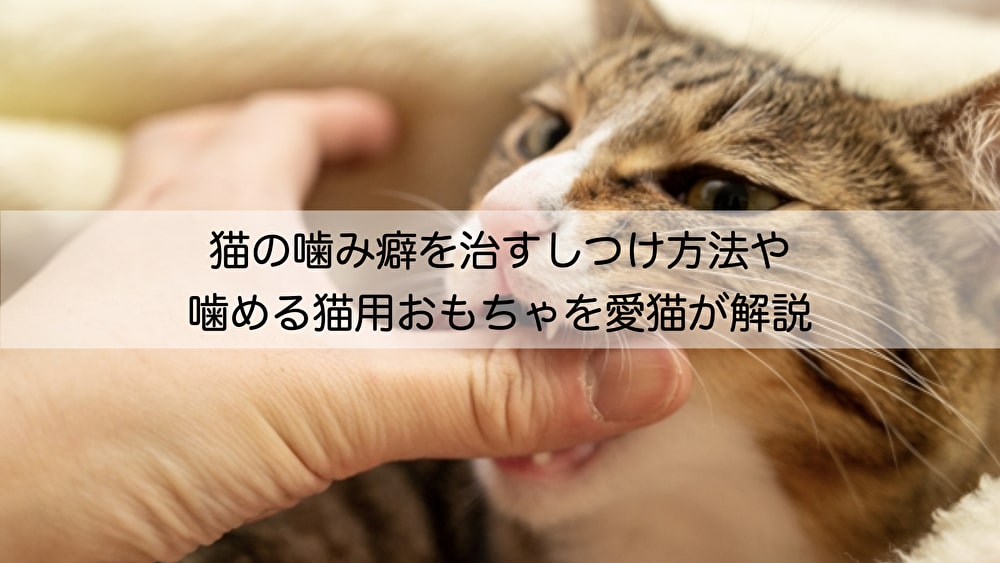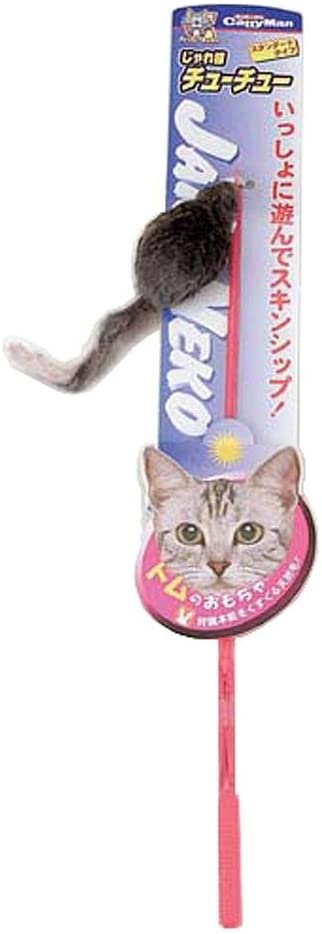「初めて猫を飼うけど、猫の噛み癖を治すしつけ方法が知りたい。」

「子猫を飼っているけど、よく猫に噛まれて困っている。」
あなたは今、そうお考えではありませんか。
猫の噛み癖を治すしつけ方法を知りたい方に向けての記事になります。

猫と暮らす上で知っておきたい猫の噛み癖を治すしつけ方法について、現役の猫の下僕が解説していくよ!!
今回は、猫の噛み癖を治すしつけ方法をまとめました。
Table of Contents
猫が噛む理由

猫はなぜ噛むのでしょうか。
猫は元々狩猟動物なので、獲物のような動きや音、ニオイにはとても敏感です。
猫はお腹が減っている時にはもちろん、獲物のようなものを見つけた時にも噛み付くことがあります。
また、反対に甘えたい時にも噛み付くこともあります。
つまり、猫は様々な理由で噛み付くと考えられます。
猫の仕草や噛み方から猫の気持ちを踏まえた上で冷静に対処するようにしましょう。
子猫が噛む理由
かまってほしい
子猫は好奇心旺盛で、子猫がもっと遊びたいと感じている時に飼い主に噛み付くことでかまってほしいとアピールすることがあります。
遊んでほしい場合には、しっかりと遊んで満たしてあげることが大切です。
遊ぶ際には、噛んでもいいおもちゃを使って遊びましょう。
手で戯れることを覚えさせてしまうと飼い主さんが怪我してしまったり、猫に危険が及んでしまうことがあります。
子猫は本来であれば最低生後2~3ヶ月までで、親兄弟とのじゃれ合いの中で噛む加減を学んでいきます。
強く噛みすぎると、兄弟からさらに強く噛みつかれたり、親猫に怒られることで、噛み加減を覚えていきます。
生後2~3ヶ月までに親兄弟と離れてしまった場合は、しつけなど飼い主さんの方で工夫をしてあげる必要があります。
成猫が噛む理由
子猫の時期からの遊びの延長で噛む場合もありますが、成猫が噛む場合には、ネガティブな理由の可能性も考えられます。
猫の仕草や噛み方から猫の気持ちを踏まえた上で冷静に対処するようにしましょう。
不快
猫によっては、触られすぎたりスキンシップを取られすぎると、嫌になる子もいます。
猫の性格に合わせて、許容範囲を見極めてあげることが重要です。
耳が横にピンと張ったり、少し後ろに伏せている状態のイカ耳にさせている、拒絶しているように嫌そうに身体をよじる、しっぽを素早くパタパタするなどしたら要注意です。
それらの反応を見たら、すぐに触るのを止めてあげることで猫にも飼い主にも不快な思いをさせずに済みますよ。
恐怖
猫は恐怖を感じている時、噛み付いてしまうことがあります。
恐怖対象に近づけない、猫に隠れる場所を与えるなど不安要素をできるだけ取り除いてあげてください。
そして猫が落ち着くまで、猫をしっかりと観察しつつ構いすぎないようにしましょう。
病気・怪我
猫の特定の部分を触ると怒ったり、攻撃的な行動をする場合は、病気や怪我の場合があります。
隠れた病気や怪我のサインの可能性もありますので、気になる場合には獣医に相談するようにしましょう。
猫に噛まれたときの対処法
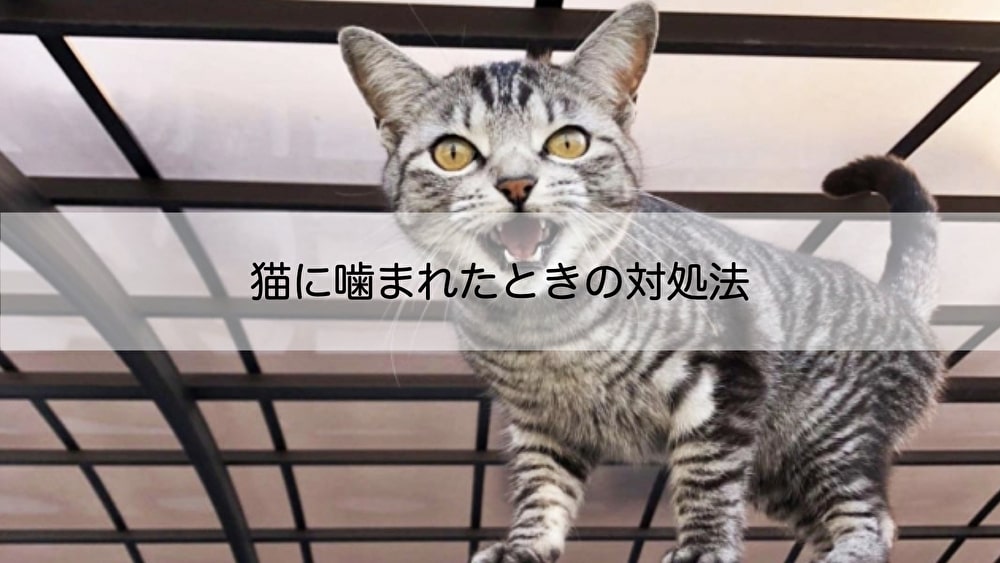
猫に噛まれたら、すぐに流水で傷口を流すようにしましょう。
深い傷や痛みがひどい時には、病院で診てもらうことをおすすめします。
猫に噛まれてしまうと、どんな病気になるのかをここからは詳しく見ていきます。
猫ひっかき病(バルトネラ症)
猫ひっかき病は、猫に寄生するノミの排泄物に含まれるバルトネラ菌が原因の感染症です。
バルトネラ菌を持ったノミの吸血によって犬や猫に感染・伝播し、その犬や猫により引っかき傷や咬み傷から人に感染します。
バルトネラ菌は猫や犬では常在菌ですので無症状ではあります。
人間の主な症状として、虫刺されのように赤く腫れ、悪化すると化膿したり、潰瘍に発展したりすることもあります。
リンパ節が腫れて痛みがある、発熱、膿疱、けいれんなどの神経症状(まれ)などを伴うこともありますが、軽傷の場合は自然に治癒します。
上記のような症状がある場合には、病院で診てもらうことをおすすめします。
パスツレラ症
パスツレラ感染症は、猫の口腔内や爪の中にいるパスツレラ菌が病原体となって起こる感染症です。
人間の主な症状として、鼻汁、肺炎、化膿性皮膚炎、関節炎、髄膜炎などを伴います。
軽度から重度までの呼吸器症状や皮膚症状など、症状が幅広く、原因がわかりにくいことがありますので注意が必要です。
また、免疫不全疾患の方、糖尿病やがんなどの全身性疾患がある方、免疫状態が低下する投薬をしている方などで重篤化することがあります。
カプノサイトファーガ感染症
イヌ・ネコの口腔内に常在している「カプノサイトファーガ」という細菌を原因とする感染症で、3種の細菌カプノサイトファーガ・カニモルサス(C. canimorsus) 、カプノサイトファーガ・カニス(C. canis)及びカプノサイトファーガ・サイノデグミ(C. cynodegmi)を原因とする感染症です。
人間の主な症状として、発熱、腹痛、吐き気、頭痛があり、重症化すると敗血症や髄膜炎に発展します。
破傷風
細菌感染によって起こる人獣共通感染症の一つです。
人間の主な症状として、口を開けにくい、首筋が張る、体が痛いなどの症状を伴います。
その後、体のしびれや痛みが体全体に広がり、全身を弓なりに反らせる姿勢や呼吸困難が現れたのちに治療が遅れると死亡します。
Q熱
猫や犬の体内にいる「コクシエラ菌」が原因の感染症で、人獣共通感染症の一つです。
人間の主な症状として、発熱、頭痛、筋肉痛や関節痛、嘔吐、下痢、腹痛、胃痛、体重減少、乾いた咳などインフルエンザに似た症状が見らます。
重症化すると心内膜炎、慢性肺炎や骨髄炎に発展するケースもあります。
噛み癖を治すしつけ方法
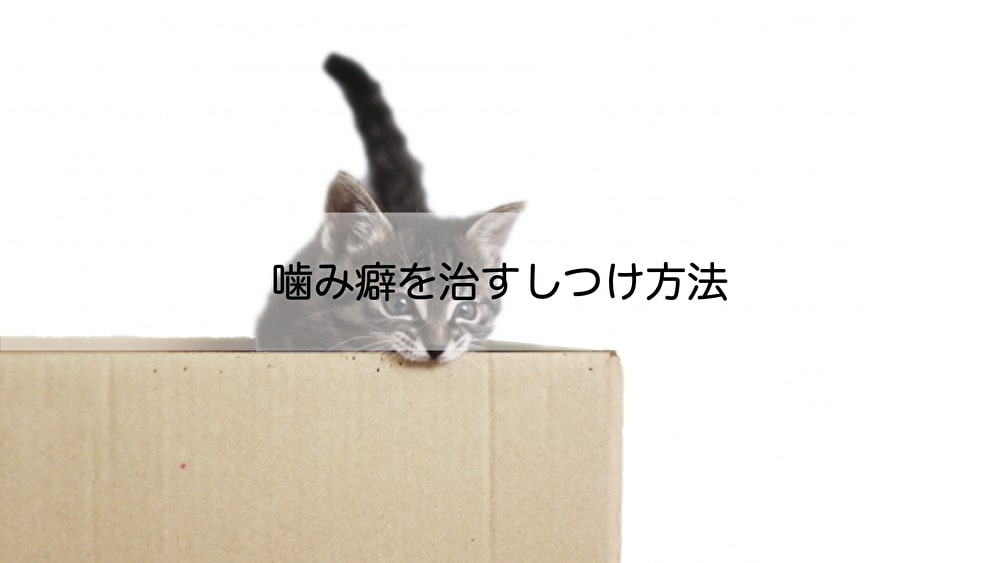
子猫の噛み癖を治すしつけ
子猫の場合は時に、噛み加減のしつけをしてあげる必要があります。
本来であれば最低生後2~3ヶ月までで、親兄弟とのじゃれ合いの中で噛む加減を学んでいきます。
強く噛みすぎると、兄弟からさらに強く噛みつかれたり、親猫に怒られることで、噛み加減を覚えていきます。
生後2~3ヶ月までに親兄弟と離れてしまった場合は、しつけなど飼い主さんの方で工夫をしてあげる必要があります。
成猫の噛み癖を治すしつけ
子猫の時期からの遊びの延長で噛む場合もありますが、成猫が噛む場合には、ネガティブな理由の可能性も考えられます。
猫の仕草や噛み方から猫の気持ちを踏まえた上で冷静に対処するようにしましょう。
【原因別】猫の噛み癖を直すしつけの方法
1.じゃれている
子猫の場合は時に、噛み加減のしつけをしてあげる必要があります。
本来であれば最低生後2~3ヶ月までで、親兄弟とのじゃれ合いの中で噛む加減を学んでいきます。
強く噛みすぎると、兄弟からさらに強く噛みつかれたり、親猫に怒られることで、噛み加減を覚えていきます。
生後2~3ヶ月までに親兄弟と離れてしまった場合は、しつけなど飼い主さんの方で工夫をしてあげる必要があります。
- 1.手を使って遊ばない
- 2.遊ぶ際には、噛んでもいいおもちゃを使う
- 3.しっかりと遊んで満たしてあげる
2.不快
大半の猫は、長時間抱っこされたり撫で続けられることが苦手な子が多いです。
自分から撫でて〜と寄ってきてもすぐにそっぽ向いたり、嫌になったら噛み付いてくるのは、猫の気まぐれさが顕著に現れていますよね。
猫の嫌サインをしっかりと見極めて、すぐに触るのを止めてあげることで猫にも飼い主にも不快な思いをさせずに済みますよ。
- 1.耳が横にピンと張ったり、少し後ろに伏せている状態のイカ耳にさせている、拒絶しているように嫌そうに身体をよじる、しっぽを素早くパタパタするなどしたら要注意
- 2.噛まれても、大声を出したり叩いたりしない
- 3.猫特有の距離感を理解する
3.恐怖
恐怖を感じた時に動物がとる<3つのF>といわれる行動があります。
それはFreeze(固まる)、Flight(逃げる)、Fight(戦う)です。
危険を感じると猫は基本的に動きを止めます。
しかしあまりにも追い詰められた恐怖を感じた際に、噛み付いてしまうことがあります。
猫が落ち着くまで、猫をしっかりと観察しつつ構いすぎないようにしましょう。
- 1.怖がられているときは距離をとる
- 2.恐怖対象に猫を近づけない
- 3.猫に隠れる場所を与える
- 3.子猫のうちから様々な環境に慣らす
4.病気・怪我
猫の特定の部分を触ると怒ったり、攻撃的な行動をする場合は、病気や怪我の場合があります。
てんかんや脳腫瘍、甲状腺機能亢進症といった病気でも攻撃するケースもありますので、日頃から普段の行動と違うことがある場合には、しっかり観察しましょう。
隠れた病気や怪我のサインの可能性もありますので、気になる場合には獣医に相談するようにしましょう。
- 1.触った部位・攻撃のパターンをよく観察
- 2.普段の行動とどう違うのかしっかりと観察
- 3.かかりつけの獣医師に相談し、体に異常がないか確認・必要があれば検査
人気の噛める猫用おもちゃ
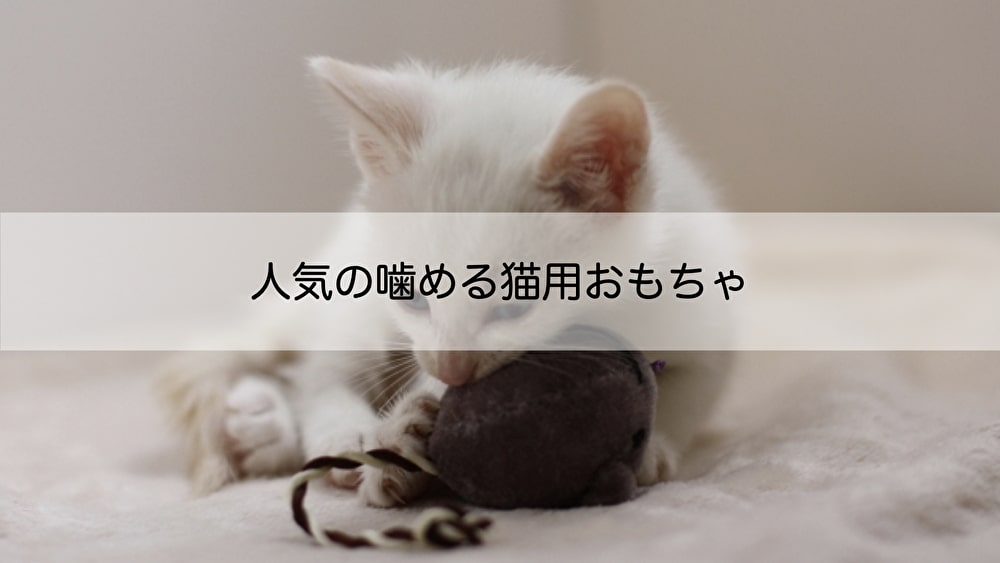
1.ペティオ (Petio) 猫用おもちゃ けりぐるみ エビ
こちらのおもちゃは愛猫と暮らし始めてからずっと購入して使っているアイテムです。
エビ、ペンギン、ハニワ、ビールなどのラインナップがあり、見た目も可愛いし、猫ちゃんの大好きなまたたび入りの蹴りぐるみです。
尻尾からカシャカシャ音が鳴り、喜んで蹴りたくなるように狩猟本能が掻き立てられるようになっています。
愛猫以外にも、預かりボランティアの時に預かっていた子猫も夢中になっていたので、どんな猫ちゃんにもおすすめできるおもちゃです。
子猫の場合には、またたび不使用の蹴りぐるみもあるので、またたび不使用の蹴りぐるみをおすすめします。
2.猫壱 キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2
2022年5月時点でAmazonの猫じゃらし・羽のおもちゃカテゴリ内でペストセラー1位のおもちゃです。
速度はゆっくり動く「初級モード」やや速く動く「中級モード」とても速く動く「上級モード」そして初級~上級をランダムに繰り返す「自動モード」の4パターン。
猫の性格や、おもちゃへの慣れに合わせてお選びいただけます。
電動タイプのおもちゃは使ったことは私自身がないので、具体的なレビューはないのですが、室内飼いで運動不足の猫たちにぴったりでおすすめです。
3.キャティーマン (CattyMan) じゃれ猫 チューチュー
こちらのおもちゃは愛猫と暮らし始めてからずっと購入して使っているアイテムです。
ネズミのおもちゃがついた釣竿タイプのおもちゃで、半年〜1年で買い替えています。
ネズミからカシャカシャ音が鳴り、尻尾が動くのも狩猟本能が掻き立てられるようになっています。
愛猫以外にも、預かりボランティアの子猫も破壊するほど夢中になっていたので、どんな猫ちゃんにもおすすめできるおもちゃです。
猫の噛み癖を治すしつけ方法のまとめ
猫の噛み癖を治すしつけ方法については以下のまとめを参考にしてください。
- 猫が噛む理由は、かまってほしい、不快、恐怖、病気・怪我の可能性もある
- 猫に噛まれてしまうと罹る可能性のある病気は、猫ひっかき病、パスツレラ症、カプノサイトファーガ感染症、破傷風、Q熱
- 猫の噛み癖を直すしつけの方法
戯れている場合は、噛み加減のしつけをしてあげる
不快な場合は、猫の嫌サインをしっかりと見極めて、すぐに触るのを止めてあげる
恐怖を感じている場合は、猫が落ち着くまで、猫をしっかりと観察しつつ構いすぎない
病気・怪我の場合は、よく観察し必要があれば獣医に診てもらう